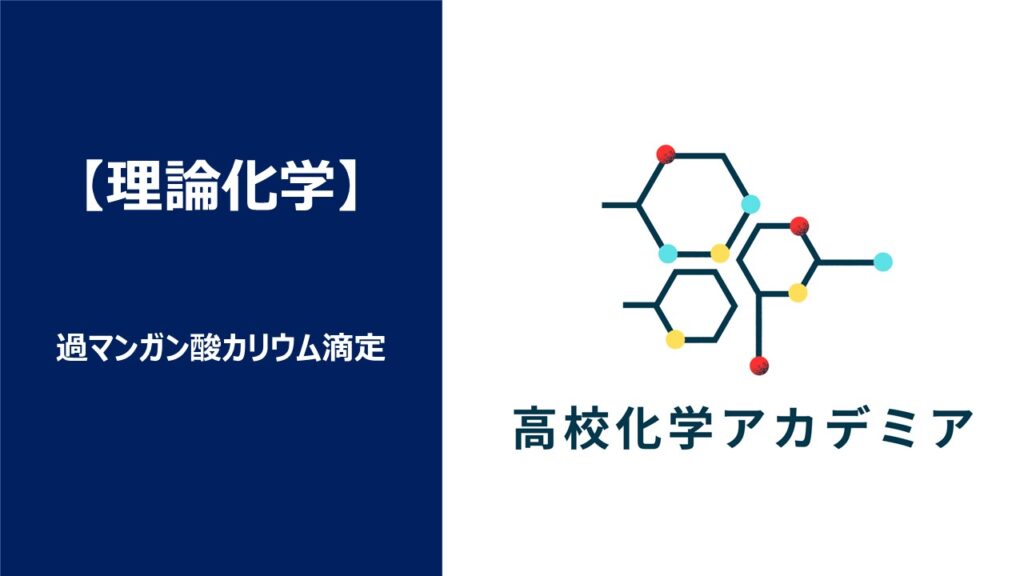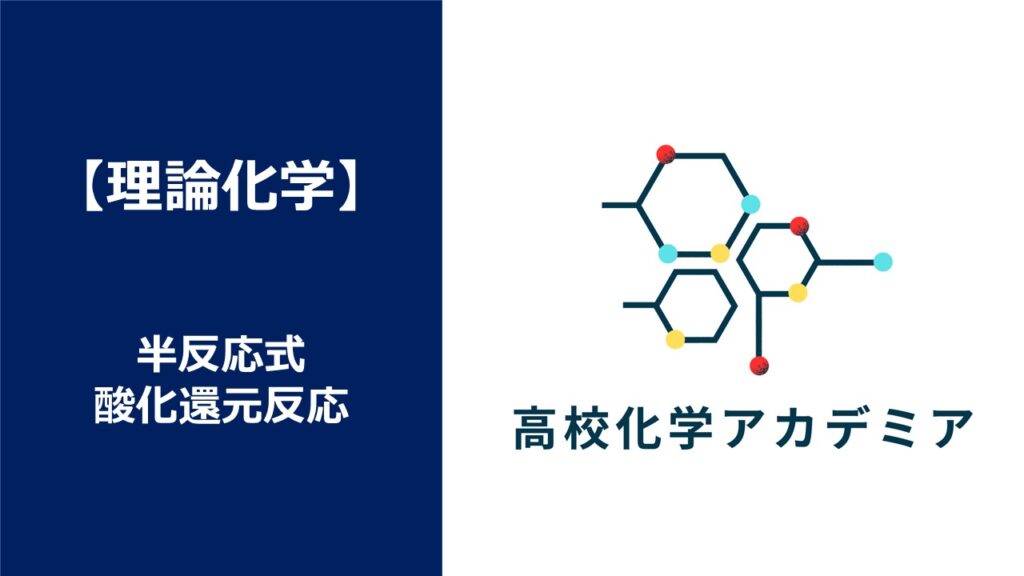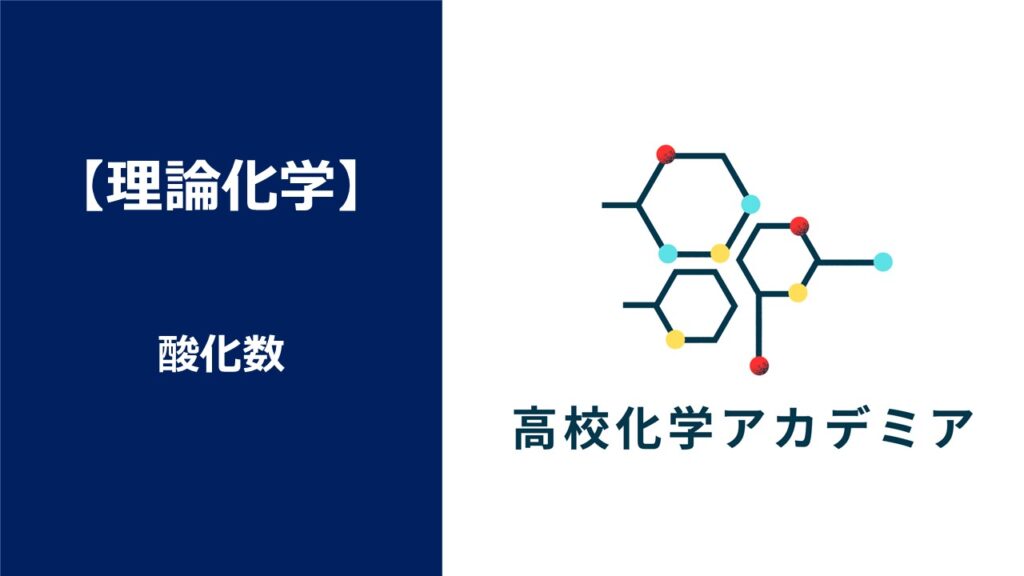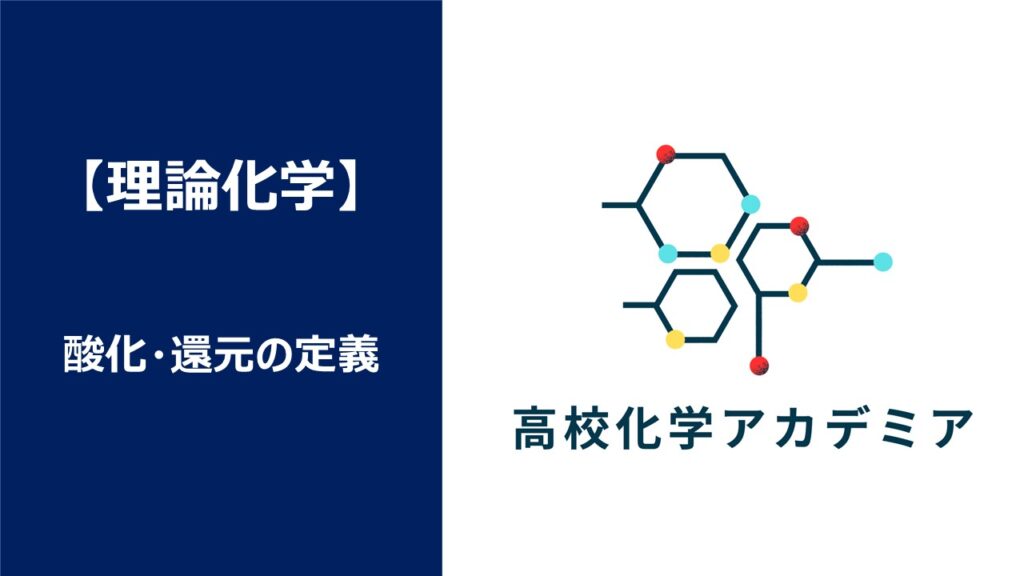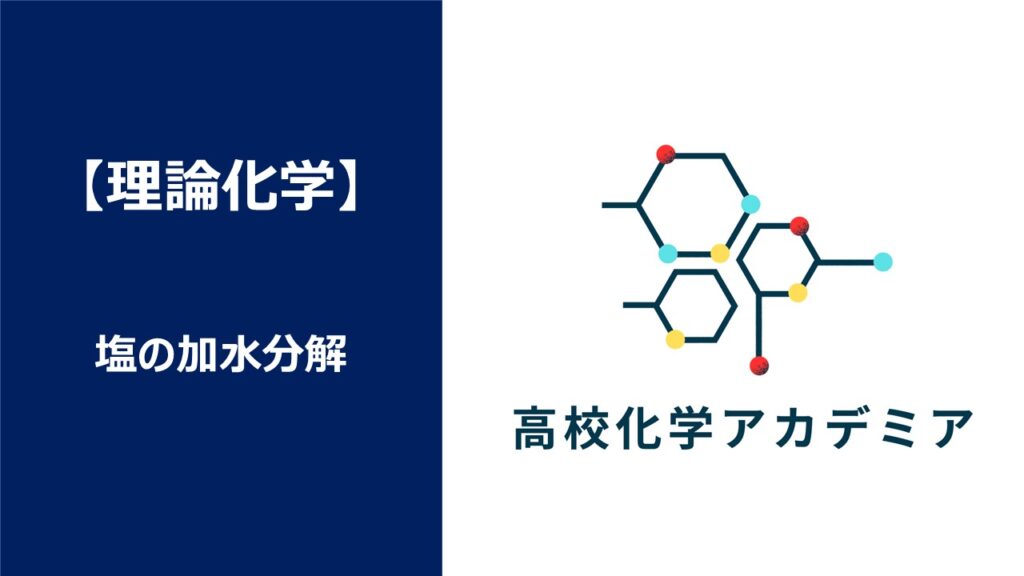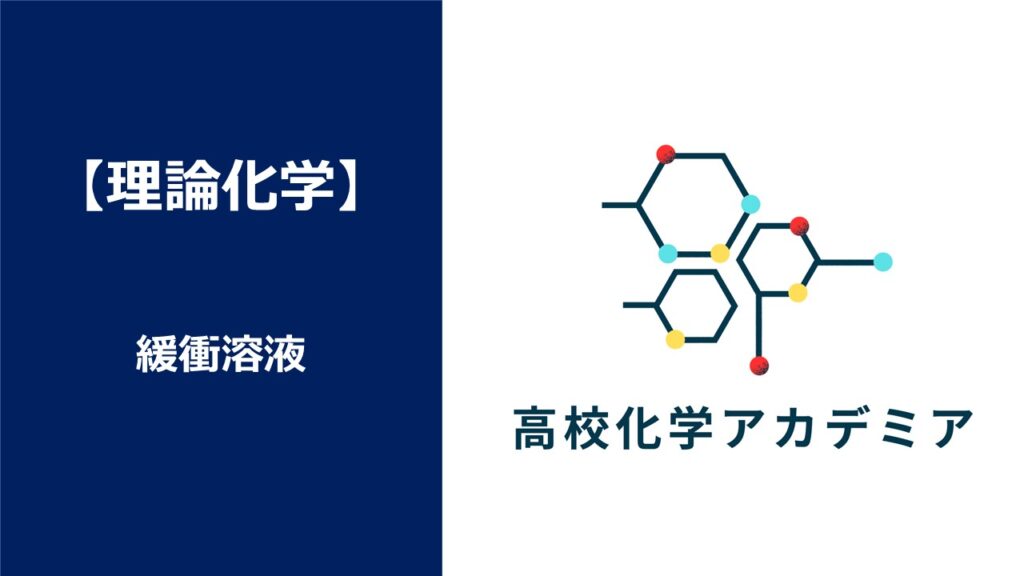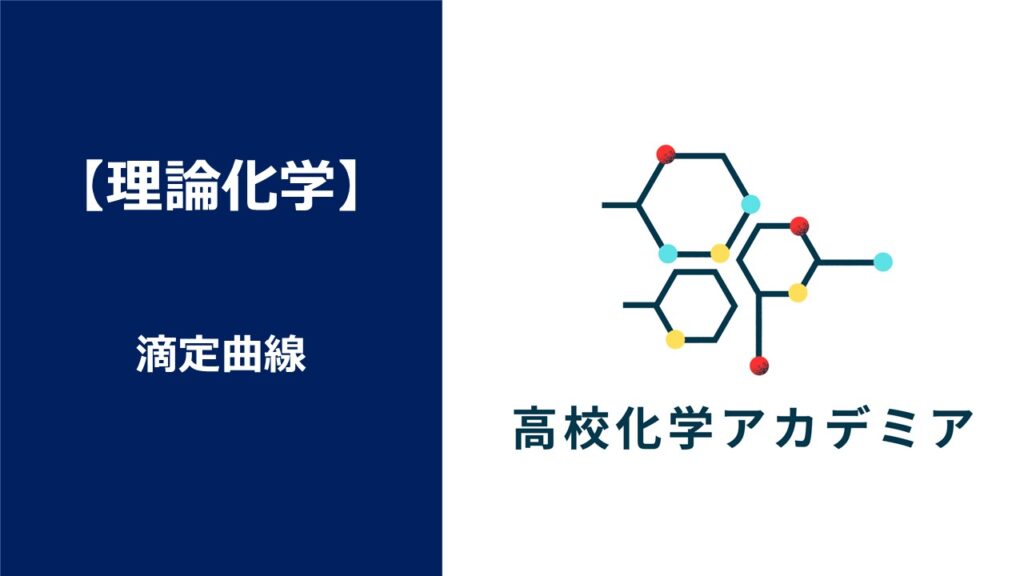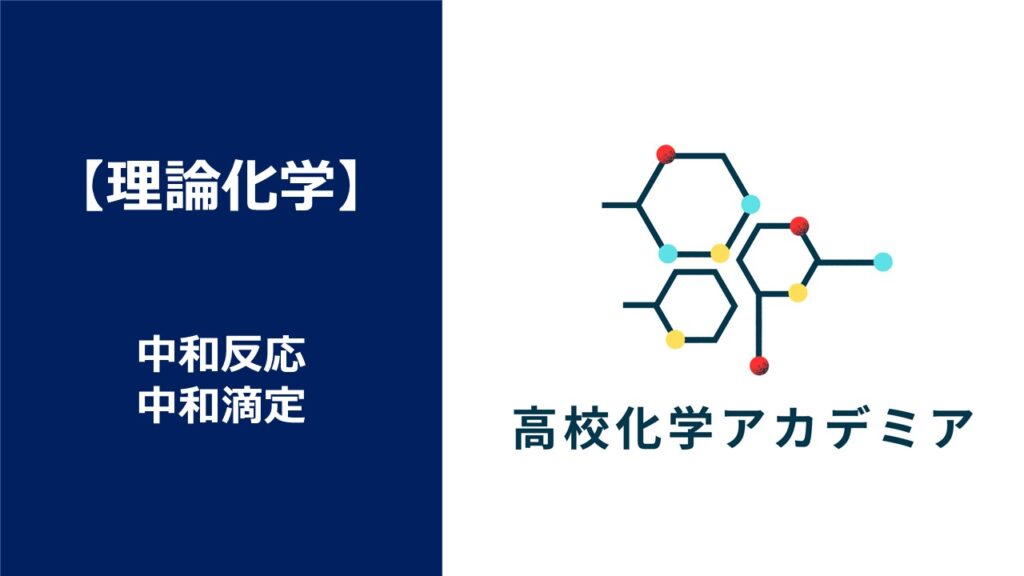2024年– date –
-

【高校化学/理論化学】ヨウ素滴定(ヨードメトリー)を9分で解説!
このページのまとめ ヨードメトリーは、ヨウ素の生成反応を利用して酸化還元滴定を行う方法。 二クロム酸カリウムや過酸化水素のような酸化剤の濃度測定に使われる。 デンプン指示薬で生成されたヨウ素が青紫色になるが、チオ硫酸ナトリウムで滴定すると無... -

【高校化学/理論化学】ヨウ素滴定(ヨージメトリー)を8分で解説!
このページのまとめ ヨウ素滴定は、酸化還元反応を利用して還元剤の濃度を測定する方法。 ヨウ素(I₂)が還元剤と反応して、I⁻に変わる過程を利用。 デンプン指示薬で青紫色が現れ、終点では色が消える。 ビタミンCや硫化物の濃度測定に使われる。 ~先生... -

【高校化学/理論化学】過マンガン酸カリウム滴定を8分で解説!
このページのまとめ 過マンガン酸カリウム滴定は、酸化還元反応を利用して、物質の濃度を計算する方法。 滴定の終点は、過マンガン酸カリウムの赤紫色が消えなくなった点で確認できる。 酸性条件でMnO₄⁻が5つの電子を受け取り、Mn²⁺に還元される。 滴定を... -

【高校化学/理論化学】半反応式・酸化還元の反応式を9分で解説!
このページのまとめ 半反応式は、酸化と還元の反応を分けて、電子の授受を示す方法。 半反応式では、酸化される側と還元される側を分けて書く。 最終的に、酸化還元反応式をバランス良くまとめることで、全体の反応式が完成する。 ~先生と生徒の会話~ 酸... -

【高校化学/理論化学】酸化数を6分で解説!
このページのまとめ 酸化数は、元素がどれだけ電子を失ったか得たかを数値で表すもの。 酸化数が増えると酸化され、減ると還元されたことを示す。 単体の酸化数は0、酸素は通常-2、水素は+1など、基本的なルールがある。 化合物を構成する酸化数の総和は化... -

【高校化学/理論化学】酸化・還元の定義を7分で解説!
このページのまとめ 酸化は電子を失う反応、還元は電子を得る反応。 酸化と還元は必ずセットで起こる。酸化剤は自分が還元され、相手を酸化させる物質。 還元剤は自分が酸化され、相手を還元させる物質。 燃焼反応、電池、呼吸など、酸化還元反応は私たち... -

【高校化学/理論化学】塩の加水分解を9分で解説!
このページのまとめ 塩の加水分解は、弱酸や弱塩基が水に溶けると、溶液が酸性や塩基性に変化する現象。 弱酸と強塩基からできた塩は、加水分解で塩基性になる。 強酸と弱塩基からできた塩は、加水分解で酸性になる。 強酸と強塩基の塩は加水分解せず、中... -

【高校化学/理論化学】緩衝溶液を9分で解説!
このページのまとめ 緩衝溶液は、pHを一定に保つために使われる溶液で、弱酸とその共役塩基、または弱塩基とその共役酸の組み合わせでできている。 酸や塩基が加わったときに、中和することでpHの変化を防ぐ。 緩衝作用はpKaに近いpHの範囲で最も強く働く... -

【高校化学/理論化学】滴定曲線を8分で解説!
このページのまとめ 滴定曲線は、滴定におけるpHの変化をグラフで表したもの。 強酸と強塩基の滴定では、S字型の曲線が描かれ、急激なpHの変化が起こる中和点がある。 強酸と弱塩基、または強塩基と弱酸の場合、pHの変化が緩やかになり、中和後のpHも酸性... -

【高校化学/理論化学】中和反応・中和滴定を9分で解説!
このページのまとめ 中和は、酸と塩基が反応して水を生成する反応で、理想的にはpHが7になる。 中和滴定は、酸や塩基の濃度を正確に測るための実験手法で、滴定によって中和点を見つける。 指示薬やpHメーターを使って、中和が完了した瞬間を判断し、濃度...

-1024x576.jpg)
-1024x576.jpg)