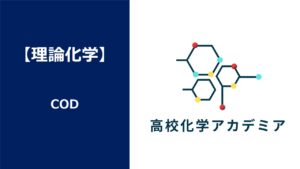このページのまとめ
- ヨードメトリーは、ヨウ素の生成反応を利用して酸化還元滴定を行う方法。
- 二クロム酸カリウムや過酸化水素のような酸化剤の濃度測定に使われる。
- デンプン指示薬で生成されたヨウ素が青紫色になるが、チオ硫酸ナトリウムで滴定すると無色になる。
- 生成されたヨウ素の量を基に、酸化剤や還元剤の濃度を計算できる。
~先生と生徒の会話~
 生徒
生徒ヨードメトリーって何ですか?ヨージメトリーと同じような感じですか?



ヨードメトリーもヨウ素を使った滴定法なんだけど、少し異なる部分があるんだ。ヨージメトリーは、酸化剤としてヨウ素を直接使って還元剤と反応させる方法だったよね。それに対してヨードメトリーでは、ヨウ素が生成される反応を利用して酸化還元滴定を行うんだよ。つまり、ヨウ素そのものを直接使うのではなく、反応で生じるヨウ素を利用するんだ。



反応でヨウ素を作って、それを滴定に使うんですね!具体的にはどんな物質を分析するときにヨードメトリーが使われるんですか?



たとえば、二クロム酸カリウムや過酸化水素のような還元剤の濃度を測定する際にヨードメトリーが使われることが多いよ。これらの酸化剤とヨウ化物イオンを反応させるとヨウ素が生成され、そのヨウ素をチオ硫酸ナトリウム(Na₂S₂O₃)などの還元剤で滴定するんだ。チオ硫酸ナトリウムがヨウ素と反応して無色になる瞬間が滴定の終点になるよ。



ヨウ素の生成反応を使うんですね。じゃあ、ヨージメトリーよりも一段階多い感じですね。



その通り!まず、反応を起こしてヨウ素を生成し、その後に滴定を行うという流れだよ。面白いことに、ヨードメトリーでは生成したヨウ素の量を使って酸化剤や還元剤の濃度を逆算できるんだ。ヨウ素は生成した後に目に見える形で色が現れるから、デンプン指示薬を加えて青紫色を確認し、反応が完了したらチオ硫酸ナトリウムで滴定する。色がなくなることで終点を確認できるんだ。



デンプン指示薬で色が変わるんですね!実際の手順ではどういう流れで行うんですか?



まず、測定したい試料に適切な量のヨウ化物イオンを加えてヨウ素を生成する。次に、生成したヨウ素にデンプン指示薬を加えて、青紫色が現れたら、チオ硫酸ナトリウムを滴定していくんだ。チオ硫酸ナトリウムがヨウ素と反応して、色が消えたら滴定の終点というわけだよ。この方法で、生成されたヨウ素の量から酸化剤や還元剤の濃度を計算できるんだ。



簡単そうに聞こえるけど、反応をしっかりコントロールする必要がありそうですね。実験室での注意点とかありますか?



そうだね、ヨードメトリーは反応条件が重要だから、酸性度や温度に気をつける必要があるよ。酸性条件が適切でないと、ヨウ素がうまく生成されなかったり、反応が進まなかったりすることがあるんだ。また、反応を正確に行うためには、酸化剤と還元剤の量や濃度もきちんとコントロールすることが大事だね。
例題&解答
【例題1】
0.01 mol/Lのチオ硫酸ナトリウム溶液を用いて、ヨードメトリーを行った。反応によって生成されたヨウ素の量が0.002 molであった場合、チオ硫酸ナトリウム溶液は何mL消費されたか求めなさい。
【解答】
反応式: I₂ + 2S₂O₃²⁻ → 2I⁻ + S₄O₆²⁻
ヨウ素1 molに対して、チオ硫酸ナトリウムが2 mol必要なので、0.002 molのヨウ素に対して0.004 molのチオ硫酸ナトリウムが必要。
チオ硫酸ナトリウム溶液の体積 = モル数 / 濃度 = 0.004 mol / 0.01 mol/L = 0.4 L = 400 mL
【例題2】
二酸化硫黄(SO₂)と反応し、ヨウ素が0.003 mol生成された。このとき、二酸化硫黄のモル数を求めなさい。
反応式: SO₂ + I₂ + 2H₂O → SO₄²⁻ + 2I⁻ + 4H⁺
SO₂とI₂は1:1のモル比で反応するため、二酸化硫黄のモル数は0.003 mol。


.jpg)
-300x169.jpg)
-300x169.jpg)