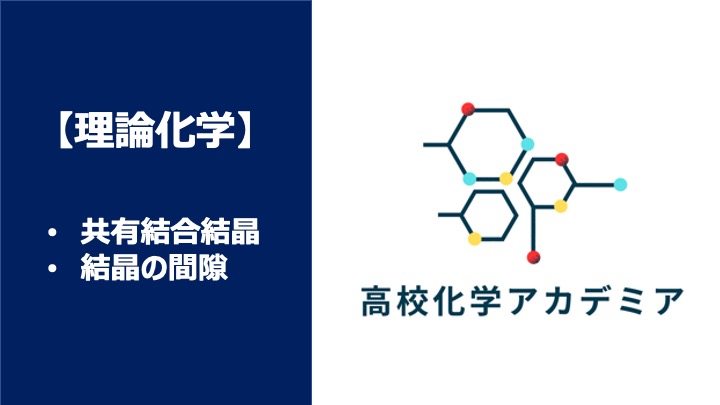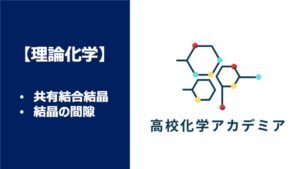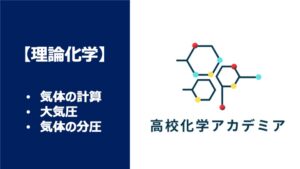今回のまとめ

このページでは、結晶格子の残りの部分として、共有結合結晶と結晶の隙間について解説していきます。共有結合結晶をとる物質はダイヤモンド、黒鉛、ケイ素、二酸化ケイ素などが知られていますが、一般的に高校化学ではダイヤモンド型結晶と黒鉛型結晶について学習していきます。ケイ素や二酸化ケイ素はおおよそダイヤモンド型結晶と同じ配置になります。また、後半では結晶の中に存在する隙間について解説します。粒子が面心立方格子を取る際にできる正四面体型隙間と正八面体型隙間について理解しておきましょう。
共有結合結晶
ダイヤモンド型結晶

まずはじめに、ダイヤモンド型結晶について解説していきます。ダイヤモンド型結晶は炭素原子が配列しており、正四面体を基準とした立体網目構造になっています。単位格子では、面心立方格子の位置と、後で学習する正四面体隙間のは半分の位置に粒子が存在しています。
正味の数は8個、配位数は4個です。配位数が4個であることは、炭素原子の原子価が4であることからも理解できます。ダイヤモンド型結晶では充填率が34%になっており、これは体心立方格子の半分と覚えておくと良いでしょう。
黒鉛型結晶

次に、黒鉛型結晶について解説していきます。黒鉛型結晶は、正六角形を基準とした平面層状構造と説明されます。上の図に示した赤い部分が単位格子になっており、正味の数は4個、配位数は3個です。黒鉛では層の間がファンデルワールス力で結合しているため、hという新しい変数が存在しています。充填率は上に示した式で計算することができます。
結晶の間隙

次に、単位格子の中に存在する隙間について解説していきます。粒子が単位格子中で面心立方格子の位置を占めるとき、格子中に2種類の隙間が存在します。1つ目が正八面体間隙で、単位格子中に合計4個存在しています。面心立方格子の位置に陰イオンを配置し、正八面体間隙に陽イオンを配置することで塩化ナトリウム型結晶をつくることができます。したがって、正八面体隙間に入ることができる粒子の条件は、塩化ナトリウム型結晶の限界イオン半径比に等しいと言えます。
2つ目の隙間は正四面体間隙で、単位格子中に8個存在しています。面心立方格子の位置に陰イオンを配置し、正四面体隙間の半分に陽イオンを配置することで閃亜鉛鉱型結晶をつくることができます。つまり、正四面体型隙間に入ることができるのは、閃亜鉛鉱型結晶の限界イオン半径比に等しいと言えます。
面心立方格子と六方最密構造の違い

単位格子を学習している中で、面心立方格子と六方最密構造が非常に似た構造であることに気づくことができます。両者はともに最密構造であり、充填率が74%になっています。どちらも正四面体を基準に粒子が配置しているという点で共通しています。しかし、面心立方格子はABCABC・・・と3層が繰り返されているのに対して、六方最密構造ではABAB・・・と2層が繰り返されています。微妙に構造が異なるので、違いも含めて理解しておきましょう。