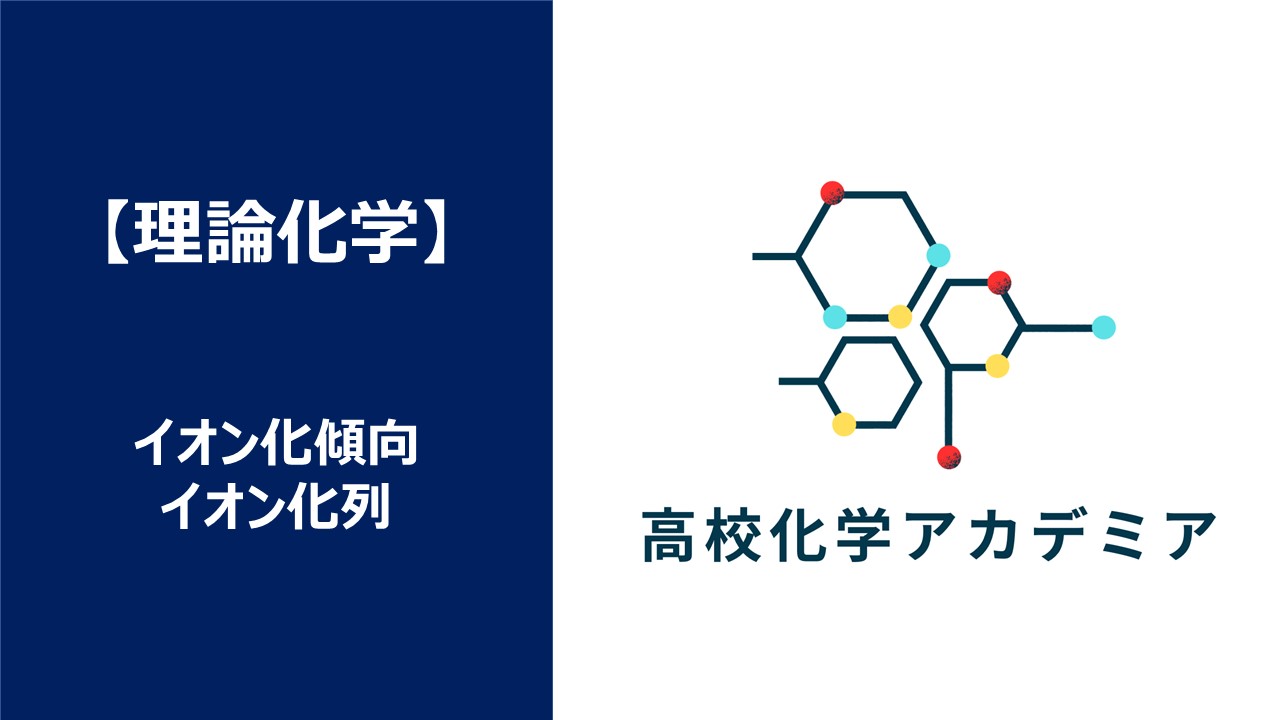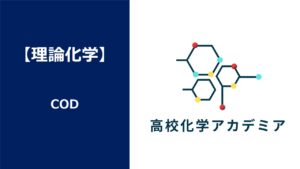このページのまとめ
- イオン化傾向は、金属がイオンになりやすい性質を示す。
- イオン化列は、金属のイオン化しやすさに基づいて並べた順番。
- 反応性の強い金属はイオン化列の上位にあり、反応性の弱い金属は下位にある。
- イオン化傾向を使って、金属の置換反応などを予測できる。
~先生と生徒の会話~
 生徒
生徒イオン化傾向って何ですか?授業で聞いたことがあるけど、まだよくわかっていません。



イオン化傾向は、金属が電子を放出して陽イオンになりやすい性質のことなんだ。言い換えると、金属がどれだけ反応しやすいかを表す指標なんだよ。例えば、リチウム(Li)やカリウム(K)は非常に反応性が高く、水と反応して簡単にイオンになる。一方で、金(Au)や白金(Pt)はほとんど反応しないし、イオンにもなりにくいんだ。この順番を整理したものが「イオン化列」だよ。



なるほど!じゃあ、イオン化列では、どの金属がどれだけ反応しやすいかがわかるってことですね?



そうだね。イオン化列では、金属の反応性の強さに応じて金属を並べているんだ。上位にある金属ほどイオン化しやすく、反応性が高い。例えば、リチウム、カリウム、カルシウム、ナトリウムなどはイオン化列の上位にある。一方で、金や銀は下位にある。こうした順番を見ることで、ある金属が他の金属よりも反応しやすいかどうかがわかるんだ。
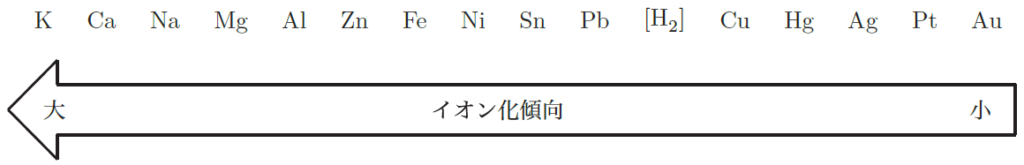
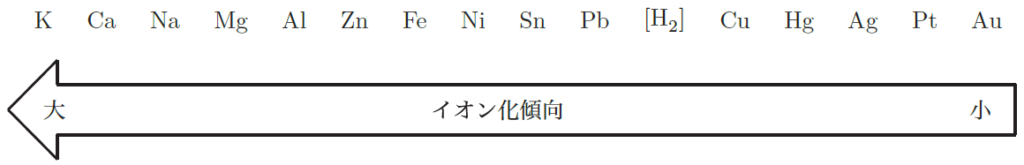



イオン化列って具体的にどうやって使うんですか?



たとえば、金属が溶液中で置換反応を起こすかどうかを予測するのに使うよ。例えば、鉄(Fe)と銅(Cu)の塩の溶液を混ぜた場合、鉄はイオン化列で銅よりも上位にあるから、鉄が銅を置換する反応が起こる。これは、鉄の方がイオンになりやすいからなんだよ。逆に、銅は鉄を置換できない。だから、イオン化列を使うと、どの金属がどれくらい活発に反応するかがわかるんだ。



それって化学反応を予測するのにすごく役立ちますね!でも、なんで金属によってイオン化しやすさが違うんですか?



それは、金属の原子が持っている電子のエネルギーや配置によるんだ。原子が電子を放出してイオンになるにはエネルギーが必要で、このエネルギーが低いほどイオン化しやすいんだよ。例えば、アルカリ金属は1つの電子を失うことで安定した電子配置になるから、非常にイオン化しやすい。逆に、金や白金は電子を失ってもあまり安定にならないから、イオン化しにくいんだ。



なるほど、金属の構造が関係しているんですね!イオン化列はどうやって覚えればいいですか?



語呂合わせを使うと覚えやすいよ!例えば、「K, Ca~」の順番を覚えるために「貸そうかな、まあ、あてにすんな、ひどすぎる借金」なんて語呂合わせがあるんだ。他にもいろいろな語呂合わせがあるから、自分に合ったものを見つけるといいよ。
例題&解答
【例題1】
次の金属のうち、イオン化傾向が最も高い金属はどれか?
銅(Cu)
鉄(Fe)
カリウム(K)
【解答】
イオン化傾向が最も高いのは、カリウム(K)
【例題2】
鉄と硫酸銅(CuSO₄)の溶液を混ぜると、どのような反応が起こるか?また、その理由を答えなさい。
【解答】
鉄が銅を置換し、硫酸鉄(FeSO₄)と銅(Cu)が生成する。
理由: イオン化列で鉄(Fe)は銅(Cu)よりも上位にあり、イオン化しやすいため。