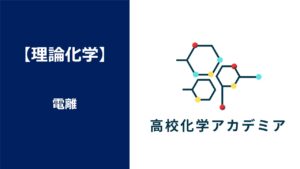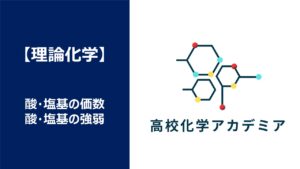このページのまとめ
- 電離は、物質が水に溶けてイオンに分かれる現象。
- 強酸・強塩基はほぼ完全に電離し、弱酸・弱塩基は部分的にしか電離しない。
- 水の「溶媒効果」により、イオン結合を持つ物質は電離しやすくなる。
- 電離度が高い物質は電気をよく通し、低い物質は電気の通りが悪い。
~先生と生徒の会話~
 生徒
生徒物質が水に溶けるときに、どうして一部が「電離」するのかよくわかっていないんですけど、電離って具体的にどういう現象なんですか?



電離は、物質が溶液中でイオンに分かれる現象を指しているんだよ。たとえば、塩化ナトリウム(NaCl)を水に溶かすと、Na⁺(ナトリウムイオン)とCl⁻(塩化物イオン)に分かれるよね。この分かれる過程が「電離」と呼ばれるんだ。物質が電離すると、その溶液は電気を通すようになるんだよ。



ああ、塩が水に溶けたときに電気を通すのは、ナトリウムと塩化物イオンに分かれているからなんですね。でも、すべての物質が電離するわけではないんですか?



その通りだね!すべての物質が電離するわけではないし、電離の程度にも違いがあるんだ。例えば、塩酸(HCl)は水に溶けるとほぼ完全に電離して、H⁺(水素イオン)とCl⁻に分かれるから「強酸」として分類されるんだよ。一方、酢酸(CH₃COOH)のような「弱酸」は、電離が部分的にしか起こらない。つまり、すべての酢酸分子がイオンに分かれるわけではないんだ。



電離の程度が違うというのは、強酸や弱酸だけでなく、塩基でも同じなんですか?



そうだね!塩基でも同じ原理が働いているよ。例えば、水酸化ナトリウム(NaOH)は水に溶けると完全に電離してNa⁺とOH⁻(水酸化物イオン)になるから「強塩基」として分類される。一方、アンモニア(NH₃)は水に溶けても部分的にしか電離しないから「弱塩基」だね。



なるほど、物質によって電離の程度が違うんですね。それって、電離がどうやって起こるかに関係があるんですか?



そうだね。電離が起こるには、溶媒である水の役割が大きいんだ。水は極性を持った分子だから、イオン結合を持つ物質を溶かすと、その極性がイオンを引き離して分解するんだ。例えば、NaClの場合、Na⁺は水分子の酸素原子と引きつけられ、Cl⁻は水分子の水素原子と引きつけられることで、電離が起こる。水のこの「溶媒効果」が電離を促進するんだよ。



なるほど、水がイオンを引き離す力を持っているから電離が起こるんですね!でも、電離しやすい物質としにくい物質の違いは何ですか?



これは物質の「電離度」によって決まるんだ。電離度が高い物質は、強い電解質として水に溶けたときにほぼ完全にイオンに分かれる。一方、電離度が低い物質は、弱い電解質として一部しか電離しない。例えば、食塩(NaCl)や塩酸(HCl)は強い電解質で、酢酸やアンモニアは弱い電解質なんだよ。



ああ、電離度が高いと完全に分かれて電気をよく通すんですね!だから、食塩水は電気を通すんですね。



その通り!電離度が高いほど、溶液中に自由に動けるイオンが多くなるから、電気をよく通すんだ。逆に、電離度が低いとイオンが少ないから、電気の通りが悪くなるんだよ。
例題&解答
【例題1】次の物質の電離について説明しなさい。
1. 塩酸(HCl)
2. (CH₃COOH)
塩酸は強酸であり、水中でほぼ完全に電離してH⁺とCl⁻に分かれる。
酢酸は弱酸であり、水中で部分的にしか電離せず、一部のCH₃COOH分子だけがH⁺とCH₃COO⁻に分かれる。
【例題2】電解質の電離度が溶液の導電性にどのように影響するかを説明しなさい。
電解質の電離度が高いほど、溶液中に存在するイオンの数が増えるため、電気をよく通す。電離度が低いと、イオンが少なくなるため、導電性が低くなる。