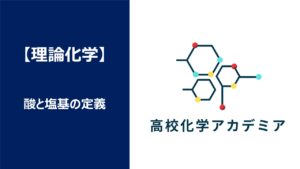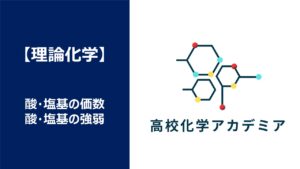このページのまとめ
- アレニウスの定義:酸はH+を放出する物質、塩基はOH−を放出する物質。
- ブレンステッド・ローリーの定義:酸はプロトン(H+)を与える物質、塩基はプロトンを受け取る物質。
- ルイスの定義:酸は電子対を受け取る物質、塩基は電子対を提供する物質。
~先生と生徒の会話~
 生徒
生徒酸と塩基ってよく出てくるけど、それぞれがどういう基準で分類されているのか、ちょっと混乱しています。酸と塩基にはどんな種類があるんですか?



良い質問だね!酸と塩基にはいくつかの分類方法があって、それぞれの定義によって違う特徴が見えてくるんだよ。主に使われるのは「アレニウスの定義」、「ブレンステッド・ローリーの定義」、そして「ルイスの定義」の3つだね。これらの定義を使って、酸と塩基がどんな性質を持っているかを理解することができるんだ。



まず、アレニウスの定義から説明しようか。この定義によれば、酸は「水に溶けて水素イオン(H+)を放出する物質」、塩基は「水に溶けて水酸化物イオン(OH−)を放出する物質」とされているんだ。例えば、塩酸(HCl)は水に溶けてH+を放出するから酸、そして水酸化ナトリウム(NaOH)は水に溶けてOH−を放出するから塩基というわけだね。



なるほど、水に溶けると何を放出するかで酸か塩基かが決まるんですね!でも、アレニウスの定義だけだとカバーできない反応もあるんじゃないですか?



その通りだよ!アレニウスの定義は水に溶ける反応に限られているから、水に関わらない反応については説明ができないんだ。そこで、次に「ブレンステッド・ローリーの定義」が役に立つ。この定義では、酸は「プロトン(H+)を与える物質」、塩基は「プロトンを受け取る物質」とされているんだ。これによって、水に溶けない反応も説明できるんだよ。



例えば、アンモニア(NH3)はアレニウスの定義では塩基として扱われないけど、ブレンステッド・ローリーの定義では、プロトンを受け取ってNH4+を作るから塩基として扱われるんだ。



ああ、プロトンのやり取りで酸や塩基を定義するんですね!それなら水に関係なくても反応を説明できそうです。じゃあ、ルイスの定義ってどう違うんですか?



ルイスの定義は、さらに広い範囲の反応を説明するためのものだよ。ルイスの定義によると、酸は「電子対を受け取る物質」、塩基は「電子対を提供する物質」とされているんだ。この定義は、プロトンのやり取りに限らず、もっと多くの反応を扱えるんだよ。



例えば、ホウ酸(BF3)はルイス酸の代表的な例だね。ホウ酸は自身でプロトンを放出することはないけれど、電子対を受け取ることができるから、ルイス酸として扱われるんだ。一方、アンモニアはルイス塩基として、電子対を提供してホウ酸と結びつくことができる。



なるほど、ルイスの定義では電子のやり取りで酸と塩基を判断するんですね!それだとかなり広い範囲の反応を説明できるわけですね。



その通り!酸と塩基を分類する定義にはそれぞれのメリットがあって、反応の状況に応じて使い分けることが大事なんだよ。工業的なプロセスや研究でも、どの定義が一番適しているかを見極めて使うんだ。
例題&解答
【例題1】次の物質について、酸または塩基として分類しなさい。NH3(アンモニア)
アンモニアはプロトン(H+)を受け取るため、塩基として分類される。
【例題2】次の反応で、どの物質がルイス酸、ルイス塩基かを説明しなさい。
BF3+NH3→F3B−NH3
ルイス酸:ホウ酸(BF3)は電子対を受け取るため、ルイス酸。
ルイス塩基:アンモニア(NH3)は電子対を提供するため、ルイス塩基。